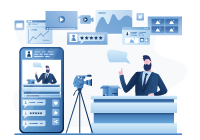タブレットとデジタル・マーケティングについて
Handbookという製品に携わり、多くのセールスツールとしてのタブレットの案件に携わる中で、「デジタル・マーケティング」という概念が、タブレットの出現により拡張され始めていることを強く感じています。
そして、私はタブレットの導入とは、多く企業においてデジタルマーケティングにおいて必須の情報機器になると考えているのです。

デジタルマーケティングの領域
デジタルマーケティングは「ネットマーケティング」(=ウェブマーケティング)とは異なります。デジタルマーケティングとは「情報通信技術を駆使し、マスやリアルを含むマーケティング全体の最適化を行うこと」です。
たとえば「マーケティング・オートメーション(MA)」や「オムニチャネル」「O2O」という概念はまさにデジタルマーケティングの領域でありリアルに関わる領域と言えます。私が長年関わってきたウェブマーケティングを包括する概念です。
もちろん、リアルのマーケティングは重要です。しかし、多くのマーケッターが交通広告や放送などのマス広告、イベントなどに限界を感じており、情報通信技術を駆使したリストに対する継続的かつ反復的なアプローチや独自コンテンツによる集客に可能性を感じているのです。
セールスパーソンが持ち歩くオウンドメディアとしてのタブレット
デジタルメディアを考えると、ウェブやメールなどのオウンドメディアの運営から、ソーシャルメディアなどのアーンドメディア、ウェブ広告などのペイドメディアの3つの分類が一般的にイメージされます。
この分類でいくと、セールスツールとしてのタブレットはオウンドメディアでしょう。つまり、タブレットとは営業パーソンが持ち運ぶオウンドメディアなのです。
以前、セールス・マーケティング・テクノロジーとしてのタブレットという記事において、Handbookとタブレットの導入が「カタログ発注」に似ていると書きました。
そして、驚くことに、全く新しい情報機器とそのソリューションという情報通信技術の導入が、
- ・クラウド化によるシステム運用負荷の軽減
- ・UX進化とマーケティング部門のリテラシー向上
- ・現場に求められる変化スピードの速さ
という理由で「カタログ発注」程度で実現できるという現実を私たちはもっと注意深く考えなければならないでしょう。
攻めの経営を実現する「デジタル」の責任者
もちろん、さきの記事では、さらにマーケティング・テクノロジーを差別化の源泉とするには、IT部門と営業マーケティング部門とのコラボレーションによるイノベーションが必要とも述べました。
こうした考え方は、特にガートナー社が提唱する「CDO(チーフ・デジタル・オフィサー)」と似たものとも言えると思います。これはCIOやCMOを包括する概念であり、ビッグデータやモバイルなどの知見による「攻めの経営」を実現する人材であると言えます。
CMOという呼称が適切かどうかは別にしても、上記のデジタルメディアとモバイル、そしてビッグデータの活用を、従来のIT部門や営業マーケティング部門という垣根を越えて実現せねばならない状況に企業は置かれていると言えるでしょう。
タブレットでウェブテクノロジーをセールスの現場に
デジタルマーケティングはウェブとリアルの双方を含む概念ですので、その魅力については、ウェブマーケティングの魅力について考えるのが一番です。
そして、タブレット導入による魅力はウェブマーケティングの魅力がセールスの現場に訪れることと言えます。
特に以下の点はウェブマーケティングが世界を変えたポイントであり、それがセールスの現場に投入されるのです。
- ・ユーザー主導のコンテンツ
- ・アクセス解析
- ・反復的最適化・ABテスト
- ・検索
- ・コンテンツのパーソナライズ
- ・リコメンデーション
デジタルマーケティングへの集中
私は紙は多様な領域で残り続けると思っていますが、今後、企業活動においては加速度的に紙はタブレットに置き換えられていくと考えます。
現在、多くの企業で、カタログを制作する部署とウェブの部署は別に存在します。そして、理論的には同様のコンテンツを制作する使命を負いながらも、両者の円滑な交流は実現できていません。
つまり、エネルギーが紙とウェブとで分散され、時に矛盾すら発生することもあります。
しかし、タブレットの導入で、コンテンツはデジタル一つでよくなります。
このことをチャンスと捕らえるべきと私は考えます。企業は全エネルギーをウェブとタブレットで実現するデジタル・プレゼンテーションに集中すべきでしょう。
ウェブとモバイルに注力し、ウェブと紙資料で分断されていた組織や顧客向け情報の統合を図る組織が力を持っていくと私は考えます。
そしてセールスの現場で、前述のウェブマーケティングの知見を活用していくべきなのです。
タブレットの導入は、そうしたデジタルマーケティングの強化という文脈でこそ考えるべきでしょう。